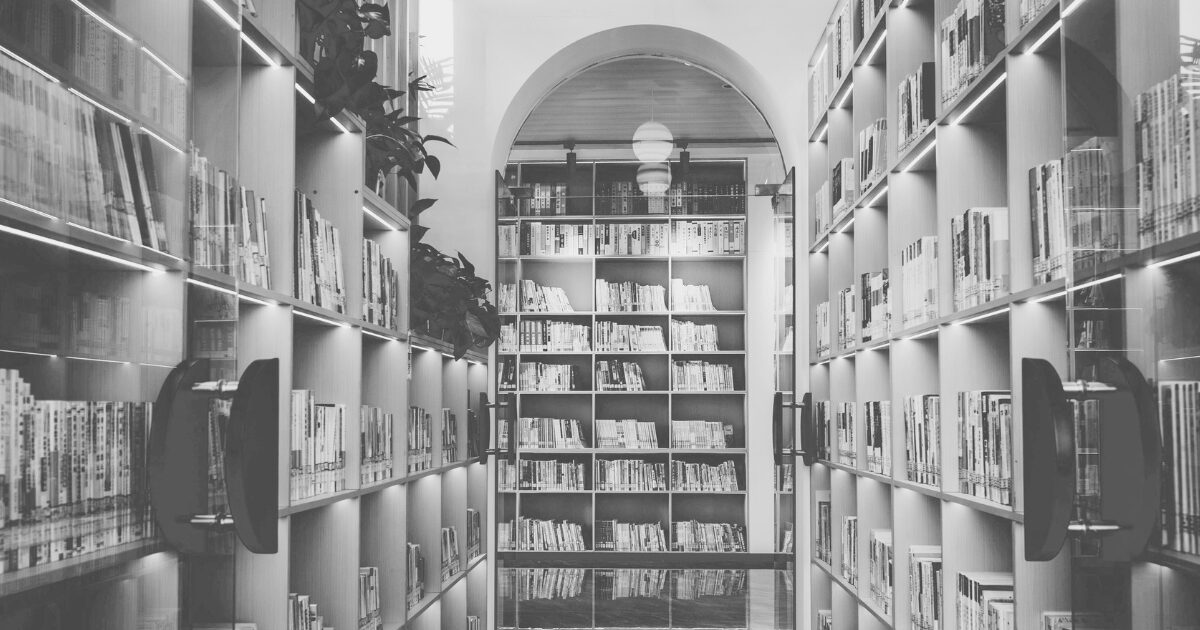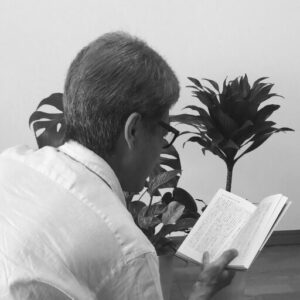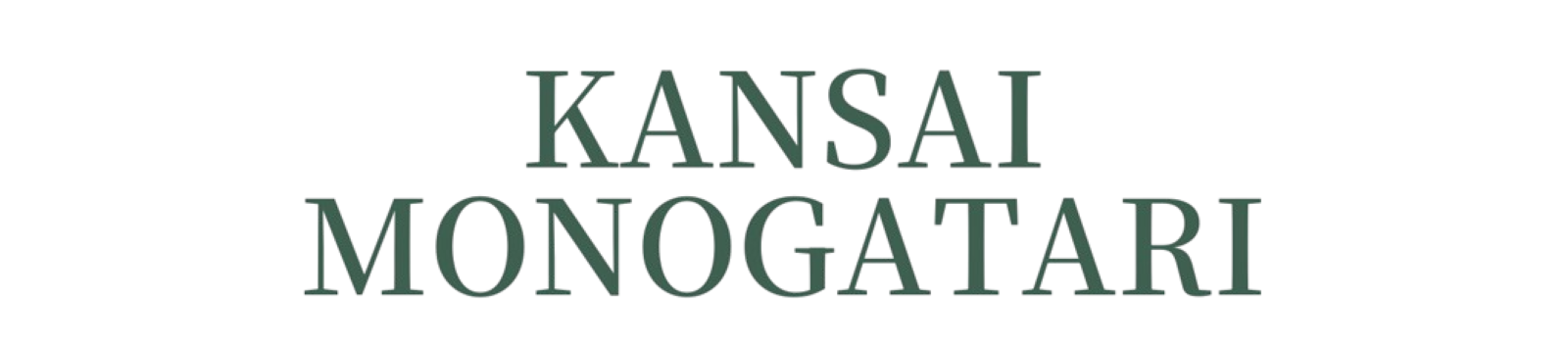『すかたん』は、大阪弁でテンポ良く進む時代小説。目次から大阪弁しか出てこない。「ちゃうちゃう」「まったり」「だんない」「ぼちぼち」・・・。もう見るからに大阪が舞台の物語とわかる見出しに、妙に興味をそそられたんです。これまで時代小説はあまり読んでなかったので、最初は、おもしろいのかな…と思いながら読み始めたのですが、大阪の旨い食べ物と人情に引き込まれる物語でした。
大阪弁のリズム感がおもしろい
この物語の大きな魅力のひとつは、なんといっても大阪弁で交わされる会話のテンポのよさ。舞台は大阪・天満の青物問屋で、出てくるのはほとんど大阪の人たち。だから、登場人物同士のやり取りがほんとにおもしろいんです。ボケとツッコミの掛け合いみたいな会話もあって、何気ない日常の場面でも、思わずクスッと笑ってしまうところが何度も出てきます。
しかも、出てくる言葉の細かいところまでちゃんと大阪弁なんです。「醤油」じゃなくて「お醤油ぅ」、「芽」は「芽ぇ」だし、「油揚げ」は「おあげさん」、「いなり寿司」は「おいなりさん」なんです。こんなふうに、語尾や言い回しひとつで、一気に大阪の空気感が広がる感じがたまりません。
関西出身の人なら、きっとこの言葉のリズム感がしっくりきて、自然に物語に入り込めると思います。私も関西人なんですが、気づいたら関西のイントネーションでセリフを読んでました。
大阪弁にあまり馴染みのない人にとっては、最初はちょっと意味が分からなかったり、「なんかキツい言い方…」って感じる部分もあるかもしれません。でも、大阪弁って、実はすごく柔らかくて勢いがあって、読み進めるとだんだん慣れて逆にクセになると思います。わからない言葉も、聞き慣れないからこそ新鮮で、むしろそれが面白かったりもするんですよね。
大阪の伝統野菜と人の温かさ

青物問屋には、旬の野菜がズラリと並び、人々が朝から晩まで懸命に働いています。ただの“野菜”じゃなくて、それを育てる人、運ぶ人、売る人…それぞれの想いがぎゅっと詰まってるのが、ちゃんと伝わってくるんです。
この物語では、そんな“青物野菜”たちもちゃんと主役。天王寺蕪、難波葱、河内蓮根…。どれも聞くだけで「ああ、あれね!」って味や香りが浮かんでくるような、大阪の伝統野菜たちです。それを使った料理の描写がまた旨そうで、読んでるだけでいい匂いが漂ってきそう。さらに、それを丁寧に育てる人たちや、大事に扱って届ける人たちの、野菜に対する愛情や誇りがしっかりと感じられます。
そして何より、野菜をきっかけに人と人とがつながっていく場面が、ほんとにあったかいんです。この物語の主人公は江戸からやってきて青物問屋の女中として働く女性。最初は言葉の意味もわからないし、うまく馴染めずに「大坂なんて、大っ嫌いっ」って感じだったんですが、店の人たちのさりげない優しさや気の利いた一言に触れて、少しずつ打ち解けていく。その様子に、「人との関わりって、こういうのがいいよなぁ」と思わされます。
“食”と“人情”。このふたつが、大阪という土地の空気と一緒に、物語のなかでとても丁寧に描かれていて、読んでいて心地いいいんです。登場人物たちはみんな、野菜と自分の仕事にまっすぐで、そこにすごく力強さがあるし、読み終わったあと、ちょっと元気をもらえたような気持ちになれます。
大阪の人情がしみる
朝井まかてさんの『すかたん』。舞台は、大阪・天満の青物問屋。江戸からやってきた未亡人・知里が、町中で出会った問屋の若旦那・清太郎や、個性豊かな人々と共に、野菜を通じて人生を再び歩み始める人情物語。テンポのいい大阪弁のやりとり、旬の野菜とその背景にあるドラマ、登場人物たちの不器用ながらもまっすぐな生き方が、じんわりと心に染みてくる一冊です。そして、いつまでも煮え切らない、知里と清太郎の恋模様も気になるところ…。
朝井まかてさんの小説を初めて読んだんですが、時代小説にあまり馴染みのない私でも、すんなりと物語に浸れました。大阪弁のリズム感もあって読みやすいし、時代小説が初めての方にもおすすめです。

Sponsored Link
Kindle Unlimitedで、もっと読書を楽しみませんか?
「Kindle Unlimited」は、幅広いジャンルの200万冊以上が読み放題になる、Amazonの読書サービス。
初めてなら30日間無料で利用でき、それ以降も月額980円で、好きなだけ読書が楽しめます。
あなたも「Kindle Unlimited」で、新しい本と出会いませんか。